ここでは、片埜神社 について紹介します。
【ポイント】
①.第11代垂仁(スジン)天皇(-29~70)時代創建と伝えられ、延喜式内社。
②.本殿主祭神は4神、合祀祭神は7神・・・合計11祭神
●建速須佐之男大神(タケハヤスサノオノタケハヤオオカミ);天照大神の弟。
●櫛稲田姫命(クシイナダヒメノミコト);建速須佐之男大神の妻
●八島士奴美命(ヤシマシネミノミコト);建速須佐之男大神と櫛稲田姫命の子。この6代後の子孫が大国主命。
●菅原道真公(スガワラミチザネコウ) ;平安中期、野見宿禰の後裔である菅原道真が祀られる。
③.片埜神社の沿革
・出雲国の豪族である野見宿禰(ノミノスクネ)が相撲に勝った恩賞として当地一帯を拝領。
・出雲の祖神「素盞鳴尊(スサノウノミコト)」と妻(櫛稲田姫命)、子(八島士奴美命)を奉祀し、土師(ハゼ)氏の鎮守とした。
・第60代醍醐天皇の名に編集された神名帳に登録された2,861社の一つ。
・平安中期、野見宿禰の後裔である菅原道真が祀られる。
・豊臣秀吉が大阪城築城の際、荒廃した神殿を鬼門鎮守として修復。
・その後、秀頼が片桐旦元を総奉行として本殿・築地などを修復。・・・この時から河内一之宮と呼ばれ始めた。
④.境内の文化財
・南門 桃山時代 府有形文化財 切妻造本瓦葺の四脚門で、総丹塗(ソウニヌリ)。通称「赤門」。
・石造灯篭 鎌倉時代 府有形文化財 火袋の梵字から神宮寺の遺品と云われている。過っては、ここに宮寺があった証。
・本殿 桃山時代 国重要文化財 三間社流造檜皮葺)豊臣秀頼再建。
・東門 室町時代 府有形文化財 棟門、本柱(円柱)が蟇股を挟み唐居敷(からいしき)を備える。
⑤.その他の見処
・神牛 :菅原道真に由来
・標柱(久須々美神社):九頭神廃寺付近にあった式内社で明治に合祀された。
・稲荷社 :
・皇大神宮遥拝所 :全国の郷社に設けられたもの。
・祀神一覧表 :近郷の小さな神社・祠をここ一宮に統合。
※ 本殿に合祀された主祭神以外の神々
・天照皇大神(アマテラススメオオミカミ):皇祖神
・品陀和気命(ホンダワケノミコト) ;応神天皇の別名
・天児屋根命(アメノコヤネノミコト) ;天孫降臨の際祝詞を唱えた。中臣連の祖。通称春日権現、春日大明神とも言う。
・八幡大神(ハチマンオオカミ) :誉田別命(ホンダワケノミコト)とも呼ばれ神宮皇后の息子。
・久那戸神(クナドノカミ) ;「くなど」は「来な処」すなわち「きてはならない所」の意味。
・久須々美大神(クススミノオオカミ) ;
・事代主命(コトシロヌシノオオカミ) ;
・鬼面 ;片埜神社の象徴・守り神とされている。
・依姫社 ;玉依姫命、大国主命、市寸島姫を命祀る。玉依姫命は神武天皇の母
⑥.広大な敷地敷地・・・明治時代には5ヘクタール
南は黄金野2丁目の一の鳥居跡から北は大阪歯科大学を含む牧野坂・牧野本町までのエリア
⑦.境外社
・朝原神社 :交通安全、道ひらき、導きの神様
・瘡神社 :菅原道真公の乗馬がこの場所に葬られ、草が瘡に転じた。
【関連写真】
 拝殿2013_05_13 金只
拝殿2013_05_13 金只 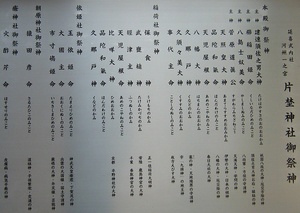 祀神一覧切出し2017_07_04 金只
祀神一覧切出し2017_07_04 金只
 依姫社2013_05_13 金只
依姫社2013_05_13 金只  鬼面2013_12_29 金只
鬼面2013_12_29 金只
 祀壇2013_05_13 金只
祀壇2013_05_13 金只  皇太神宮遥拝所2013_12_29 金只
皇太神宮遥拝所2013_12_29 金只
【補足説明】
①.片埜神社概要
・社格等 :式内社(小) (称)河内国一宮、旧郷社
・創建 :垂仁天皇年間(紀元前29年-70年)
・本殿様式:三間社流造
・例祭 :10月15日
・主な神事:お火焚祭(みかん撒き)(12月13日)
:えびす祭(1月9日-11日)
・主祭神 :建速須佐之男大神、菅原道真
・配神 :櫛稻田姫命、八嶋士奴美神
【参考情報】
Wikipedia:片埜神社
Wikipedia:スサノオ・・・・・天照大神の弟でヤマタノオロチ退治を為す
Wikipedia:櫛稻田姫命・・・・須佐之男の妻
Wikipedia:八嶋士奴美神・・・須佐之男の子である国津神
Wikipedia:菅原道真
Wikipedia:野見宿禰
Local Wiki:野見神社(野見町)
Local Wiki:野見神社(上宮天満宮)
Local Wiki:日本の神々・・・以下Wikipediaで紹介


